「事務」とは、行動に変えるための“技術”だった
坂口恭平さんの著書『生きのびるための事務』を読んで印象的だったのは、「事務」という言葉の再定義です。
単なる事務作業ではなく、抽象的な感情や考えを数字や言葉に置き換え、現実的な行動に変換する技術こそが「事務」だと語られています。
「夢を描こう」「目標を立てよう」とよく言われますが、抽象的な理想のままでは、具体的な一歩を踏み出せません。
この本が教えてくれたのは、「具体的に見える化」しない限り、現状は何も変わらないという現実でした。
📘 数字で夢を“見える化”する方法
たとえば「フリーランスとして独立したい」と思っても、何から始めればいいかわからず、時間だけが過ぎてしまうことがあります。
本書では、以下のような問いを通して夢や不安を“数字”で整理する手法が紹介されていました。
- 今の生活費はいくらか?
- 最低限必要な収入は?
- その収入を得るには、どんな仕事をどのくらいやる必要があるか?
これにより、現在地とゴールの距離が見える化され、現実的なプランが立てられるようになります。
🧭 夢を行動に変える「事務力」は、すべてに応用できる
この考え方は、ブログ運営にもそのまま応用できます。
- 自分はなぜブログを書くのか?
- 月にどれくらい稼ぎたいのか?
- そのためには1記事あたり何PV必要か?
こうした目標を明確にし、「数字」に落とし込むことで、感情や気分に左右されず、ブレずに進み続けることができます。
🌱 好きなことを続けるために、評価を手放す
本書でもう一つ心に残ったのは、「好きなことは継続すべき」というメッセージです。
ただし、私たちはすぐに「これは意味があるのか?」「うまくできているのか?」と他人の目線で自己評価をしてしまいがちです。
「失敗とは、他人の評価によって決まるもの。自分で自分を評価するべきではない」
この言葉は、純粋に「好きだからやる」という気持ちを守るために、評価を切り離すことの大切さを教えてくれました。
🔄 評価をやめることで、「継続」がラクになる
たとえばブログを書いていて、アクセス数が伸びなかったり収益が出なかったりすると、「向いていない」と落ち込んでしまうことがありますよね。
でもそこで自分を責めるのではなく、ただ「習慣」にして続けることが大切です。
- 上手くやろうとしない
- 評価されなくても書く
- 好きだからやる。それでOK
このシンプルな考え方に切り替えるだけで、自然と続けられるようになります。
🎯 自信がなくなったときは「評価」ではなく「行動」を見直す
「好き」に自信が持てないときこそ、他人の評価を手放し、「自分が心地よく続けられるかどうか」に意識を向けてみてください。
評価を止めたとき、本当の意味での“継続力”が芽生えます。
❌ 自分を否定しない。「うまくいかなかった=方法が合っていないだけ」
『生きのびるための事務』には、こんな言葉もありました。
「上手くいく」とは、「やり方が合っていた」ということ。
否定すべきは「己」ではなく、己が選んだ「方法」のみである。
うまくいかないとき、自分を責めるのは簡単ですが、それでは前に進めません。
大切なのは、「自分ではなくやり方を疑うこと」。この視点の転換が、継続への大きなヒントになります。
🔁 続かない原因は「自分」ではなく「やり方」かもしれない
- 食事制限がキツすぎた → 少し緩めてみる
- 毎日更新が負担 → 週1でもいい
- SNSで伸びない → 別の発信方法を試す
「変えるべきは戦略」であって、「自分」ではない。
これは、ブログに限らずすべての行動に通じる考え方です。
🌱 継続とは、試行錯誤の繰り返し
結果が出ないからといって、落ち込む必要はありません。
本書は、「事務的に」「冷静に」やり方を変えていく姿勢を教えてくれました。
「継続できる方法」を見つけるために、「うまくいかない方法」を経由するのは当たり前。
このプロセスを大切にすることで、自然と自分に合ったやり方が見つかっていくはずです。
🙁 正直な感想:後半はやや物足りなさを感じた
前半は「事務」という言葉への見方が変わる内容でワクワクしたのですが、後半は熱量が落ち着いてしまいました。
「好きなことだけやればうまくいく」と繰り返されるものの、
その“好き”をどう見つけ、どう形にしていくかという実践的な部分がもう少し深掘りされていたら、より多くの読者に刺さる内容になったかもしれません。
📌 理想論だけでは届かない現実もある
「好きなことを仕事にする」「評価を気にせず生きる」という考え方には強く共感しましたが、
それを実現するには一定の仕組みや生活基盤、環境の整備が必要であることも事実です。
理想と現実のバランスにもう少し触れてくれていれば、より実践的な指南書として多くの人に刺さったのでは…と感じました。
🤝 それでも、「考え方の再構築」が得られる一冊
とはいえ、前半の「抽象を見える化する」「評価を手放す」「自己否定ではなくやり方を変える」といった視点の切り替えは、私自身の思考にも大きなインパクトを与えてくれました。
読後には、自然とノートを広げて「自分にとっての“事務”」を始めたくなる――
そんな力を持った、読後に手が動く実践的なエッセイであることは間違いありません。


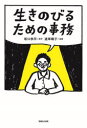



コメント